こんにちは!最近のアプリケーション開発で「サーバーレス」や「コンテナ」という言葉をよく聞きませんか?
「どちらを選べばいいの?」「それぞれの違いは何?」と悩んでいる方も多いと思います。
私も最初は同じでした。Lambda、ECS、EKS…たくさんのサービスがあって、どれを使えばいいか全然分からない状態でした。
でも大丈夫です!一度整理して理解すれば、それぞれの特徴と適用場面がクリアに見えてきます。
今回は「図解即戦力 Amazon Web Servicesのしくみと技術が これ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]」を参考に、AWS Lambdaを中心としたサーバーレス技術と、ECS・EKSのコンテナサービスについて分かりやすく解説していきます!
サーバーレスとコンテナ、どちらを選ぶべき?
現代のアプリケーション開発の選択肢
アプリケーションを開発・運用する方法は、近年大きく変化しています。
従来の方法:
- 物理サーバーや仮想マシンに直接アプリを配置
- サーバーの管理・保守が必要
- スケールアップ・ダウンが手動
現代の選択肢:
- サーバーレス: サーバー管理不要、自動スケール
- コンテナ: アプリの可搬性向上、効率的なリソース利用
- マネージドサービス: インフラ運用をクラウド事業者に委託
この中でも特に注目されているのが、サーバーレスとコンテナの技術です。
サーバーレスとコンテナの基本的な違い
まず、それぞれの基本概念を整理してみましょう。
サーバーレス(AWS Lambda):
- サーバー管理が完全に不要
- 関数単位でのコード実行
- 使った分だけの従量課金
- 自動的なスケーリング
コンテナ(ECS/EKS):
- アプリケーションを軽量な仮想環境で実行
- 開発環境と本番環境の一致
- 効率的なリソース利用
- Dockerなどの技術を活用
どちらも「従来のサーバー管理の手間を減らす」という目的は同じですが、アプローチが異なります。
選択の基準:
- 処理時間: 短時間ならLambda、長時間ならコンテナ
- 実行頻度: 不定期ならLambda、常時稼働ならコンテナ
- アプリの複雑さ: シンプルならLambda、複雑ならコンテナ
これらの違いを理解することで、適切な技術選択ができるようになります。
AWS Lambdaでサーバーレス開発を始めよう
AWS Lambdaとは何か
AWS Lambdaは、AWSが提供するサーバーレスコンピューティングサービスです。
Lambdaの特徴:
- サーバー管理不要: インフラの設定・保守が一切不要
- 自動スケーリング: リクエスト数に応じて自動で処理能力を調整
- 従量課金: 実行時間とメモリ使用量に基づく課金
- 多言語サポート: Python、Node.js、Java、C#、Go、Rubyなど
Lambdaの動作仕組み:
- イベントが発生(APIリクエスト、ファイルアップロードなど)
- Lambdaが自動で起動
- コードを実行
- 結果を返して自動終了
このシンプルな仕組みにより、開発者はビジネスロジックに集中できます。
サーバーレスアーキテクチャのメリット
サーバーレスアーキテクチャを採用することで、多くのメリットが得られます。
開発・運用面のメリット:
- 開発速度の向上: インフラ設定が不要で、コード開発に集中
- 運用負荷の軽減: サーバー管理、セキュリティパッチ適用が不要
- 自動スケーリング: トラフィック変動への自動対応
コスト面のメリット:
- 初期費用ゼロ: サーバー購入や設定費用が不要
- 使用分のみ課金: アイドル時間の費用が発生しない
- 運用費削減: 人的リソースの削減が可能
技術面のメリット:
- 高可用性: AWSが自動で冗長化・障害対応
- セキュリティ: AWS側でセキュリティ対策を実施
- 最新技術: 常に最新のランタイム環境を利用可能
これらのメリットにより、特にスタートアップや小規模開発チームで人気が高まっています。
Lambdaの実行環境と制限事項
Lambdaを使う際に知っておくべき制限事項があります。
主な制限事項:
- 実行時間: 最大15分
- メモリ: 128MB~10,240MB
- 一時ディスク容量: /tmpディレクトリで最大10GB
- パッケージサイズ: 直接アップロード250MB、S3経由50MB
適用場面の例:
- 適している: Webアプリのバックエンド処理、データ変換、画像リサイズ
- 適していない: 長時間バッチ処理、大容量ファイル処理、常時稼働アプリ
これらの制限を理解することで、Lambdaが適用できるかどうかを判断できます。
コンテナサービスECSとEKSの特徴
Amazon ECS(Elastic Container Service)の概要
Amazon ECSは、AWSが提供するコンテナオーケストレーションサービスです。
ECSの特徴:
- AWS独自: AWSに最適化された設計
- シンプル: 学習コストが比較的低い
- フルマネージド: インフラ管理をAWSが担当
- 他AWSサービスとの統合: IAM、CloudWatch、ALBなどとのシームレス連携
ECSの主要コンポーネント:
- クラスター: コンテナを実行するリソースの集合
- タスク定義: コンテナの実行設定(CPUやメモリなど)
- サービス: タスクの実行数を管理・維持
ECSは「AWSでコンテナを簡単に使いたい」という場合に適しています。
Amazon EKS(Elastic Kubernetes Service)の概要
Amazon EKSは、Kubernetesを使ったコンテナオーケストレーションサービスです。
EKSの特徴:
- Kubernetes標準: 業界標準のKubernetesを使用
- ポータビリティ: 他のクラウドやオンプレミスでも同じ設定
- 豊富なエコシステム: Kubernetesの豊富なツール群を活用
- 高度な機能: 複雑なアプリケーション管理に対応
Kubernetesの主要概念:
- Pod: コンテナの実行単位
- Deployment: Podの管理・スケーリング
- Service: ネットワーク経由でのPodアクセス
EKSは「Kubernetesの知識を活用したい」「複雑なマイクロサービスを管理したい」場合に適しています。
ECSとEKSの違いと選び方
ECSとEKSのどちらを選ぶかは、チームの状況と要件によります。
ECSを選ぶべき場合:
- AWS中心の開発・運用
- シンプルなコンテナアプリケーション
- Kubernetesの学習コストを避けたい
- AWSサービスとの密結合でOK
EKSを選ぶべき場合:
- Kubernetesの知識・経験がある
- マルチクラウドやハイブリッド環境
- 複雑なマイクロサービスアーキテクチャ
- Kubernetesエコシステムを活用したい
学習コストの比較:
- ECS: AWS特有の概念のみ学習すればOK
- EKS: Kubernetes全般の知識が必要
まずは要件を整理して、どちらが自分のプロジェクトに適しているかを判断しましょう。
API GatewayとLambdaの組み合わせ
Amazon API Gatewayの役割
API Gatewayは、RESTやWebSocket APIを作成・管理するためのサービスです。
API Gatewayの機能:
- API管理: バージョン管理、ドキュメント生成
- 認証・認可: IAM、Cognito、Lambda オーソライザー
- レート制限: API呼び出し回数の制御
- キャッシュ: レスポンスのキャッシュでパフォーマンス向上
Lambdaとの連携メリット:
- サーバーレスでAPIを構築可能
- 自動スケーリング
- 従量課金モデル
- 高可用性
この組み合わせにより、インフラ管理不要でWebAPIを構築できます。
サーバーレスWebAPIの構築方法
API Gateway + Lambdaでの典型的な構築パターンを見てみましょう。
基本的な構成:
- フロントエンド: Webアプリやモバイルアプリ
- API Gateway: HTTPリクエストを受信
- Lambda: ビジネスロジックを実行
- データベース: DynamoDBやRDSにデータ保存
実装の流れ:
- Lambda関数を作成(Python、Node.jsなど)
- API Gatewayでエンドポイントを定義
- LambdaとAPI Gatewayを連携
- 認証・認可の設定
- デプロイとテスト
メリット:
- インフラ管理不要
- 自動スケーリング
- 高い可用性
- 素早いプロトタイピング
この構成は、特にWebアプリケーションのバックエンドAPIとして人気です。
EventBridgeとの連携パターン
Amazon EventBridgeを使うことで、イベント駆動アーキテクチャを構築できます。
EventBridgeの特徴:
- イベントルーティング: 様々なソースからのイベントを適切な宛先に配信
- カスタムイベント: 独自のイベントを定義・配信
- スケジューリング: 定期実行やcron風のスケジュール
Lambdaとの連携例:
- 定期バッチ処理: スケジュールに基づいてLambdaを実行
- イベント処理: S3のファイルアップロードをトリガーにLambda実行
- マイクロサービス連携: サービス間のイベント通信
この組み合わせにより、疎結合で拡張しやすいアーキテクチャを構築できます。
DevOpsとコンテナオーケストレーション
DevOpsでのコンテナ活用
DevOpsにおいて、コンテナ技術は重要な役割を果たします。
DevOpsでのコンテナメリット:
- 環境の一致: 開発・テスト・本番環境での一貫性
- デプロイの高速化: イメージベースの素早いデプロイ
- ロールバック: 以前のバージョンへの迅速な復旧
- スケーラビリティ: 需要に応じた迅速なスケール
CI/CDパイプラインでの活用:
- ソースコード管理: Git での変更管理
- ビルド: コンテナイメージの自動作成
- テスト: コンテナ環境での自動テスト
- デプロイ: ECS/EKSへの自動デプロイ
この流れにより、開発から本番運用までの自動化が実現されます。
CI/CDパイプラインとの統合
AWSでは、コンテナと相性の良いCI/CDサービスが提供されています。
主要なCI/CDサービス:
- AWS CodeCommit: Gitリポジトリサービス
- AWS CodeBuild: ビルドサービス
- AWS CodeDeploy: デプロイサービス
- AWS CodePipeline: CI/CDパイプラインオーケストレーション
典型的なパイプライン:
- CodeCommitへのプッシュをトリガー
- CodeBuildでコンテナイメージをビルド
- Amazon ECRにイメージをプッシュ
- CodeDeployでECS/EKSにデプロイ
AWS CodeBuild・CodeDeploy・CodePipelineとの連携
各サービスの役割と連携方法を詳しく見てみましょう。
AWS CodeBuild:
- ソースコードからコンテナイメージを自動作成
- Dockerfileに基づくビルド
- テストの自動実行
- Amazon ECRへのイメージプッシュ
AWS CodeDeploy:
- ECS/EKSへの安全なデプロイ
- ブルー/グリーンデプロイメント
- カナリアリリース
- 自動ロールバック
AWS CodePipeline:
- 全体のワークフロー管理
- 複数段階のパイプライン
- 手動承認ステップ
- 他AWSサービスとの統合
これらのサービスを組み合わせることで、本格的なDevOpsパイプラインを構築できます。
実際の開発現場での使い分け指針
Lambdaが適しているケース
以下のような場面では、Lambdaの採用を検討してみてください。
処理特性:
- 短時間処理: 数秒~数分で完了する処理
- 不定期実行: イベント駆動の処理
- ステートレス: セッション管理が不要な処理
具体的な用途例:
- Web API: RESTful APIのバックエンド
- 画像処理: アップロードされた画像のリサイズ
- データ変換: CSVからJSONへの変換処理
- 通知処理: メールやSNS通知の送信
- ログ処理: CloudWatchログの解析
コスト面での適用:
- アクセス数が不定期・少量
- アイドル時間が長い
- 初期投資を抑えたい
これらの条件に当てはまる場合、Lambdaは非常に効果的です。
ECS/EKSが適しているケース
一方、コンテナサービスが適している場面もあります。
処理特性:
- 長時間処理: 数時間のバッチ処理や常時稼働
- ステートフル: セッション管理やキャッシュが必要
- 複雑な処理: 複数のプロセスやサービスの連携
具体的な用途例:
- Webアプリケーション: 常時稼働するWebサーバー
- バッチ処理: 大量データの分析・変換
- リアルタイム処理: チャットアプリ、ゲームサーバー
- 機械学習: 学習モデルの推論サーバー
- データベース: キャッシュサーバーやカスタムDB
技術面での選択理由:
- 既存のDockerコンテナ資産を活用
- Kubernetesの知識・ツールを活用(EKS)
- 複雑なネットワーク設定が必要
ハイブリッド構成の考え方
実際のシステムでは、LambdaとECS/EKSを組み合わせることも多いです。
組み合わせパターン例:
1. フロントエンド処理 + バックエンド処理
- API Gateway + Lambda: ユーザーリクエストの受付
- ECS: 重い計算処理やデータ処理
2. イベント処理 + 常駐処理
- Lambda: S3ファイルアップロード時の前処理
- EKS: 機械学習モデルでの推論処理
3. マイクロサービス構成
- Lambda: 認証・認可サービス
- ECS: ビジネスロジックサービス
- EKS: データ処理サービス
設計のポイント:
- 各サービスの特性を理解
- 処理の性質に応じた適切な選択
- コストとパフォーマンスのバランス
- 運用・保守の容易さ
このようなハイブリッド構成により、各技術の強みを最大限活用できます。
サーバーレス・コンテナ技術を深く学ぶために
書籍で学べる実践的な設計パターン
今回の記事では、Lambda、ECS、EKSの基本概念と使い分けをご紹介しました。
「図解即戦力 Amazon Web Servicesのしくみと技術が これ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]」では、さらに実践的な内容が詳しく解説されています。
書籍で学べる詳細内容:
- アーキテクチャパターン: 実際のシステム設計事例
- セキュリティ対策: IAMロール、VPC設定の詳細
- モニタリング: CloudWatchでの監視設定
- コスト最適化: 料金を抑える設定テクニック
- トラブルシューティング: よくある問題と解決方法
特に図解が豊富なので、複雑なアーキテクチャも視覚的に理解できます。
実務で役立つポイント:
- Step Functionsによるワークフロー管理
- Cognitoによるユーザー認証
- SQS/SNSによる非同期処理
- CloudFormationによるインフラ自動化
これらの内容を学ぶことで、より実践的なシステムを構築できるようになります。
次に学ぶべき関連技術
サーバーレス・コンテナ技術を理解したら、次はこれらの技術も学習することをおすすめします:
インフラ自動化:
- AWS CloudFormation: インフラのコード化
- AWS CDK: プログラミング言語でインフラ定義
- Terraform: マルチクラウド対応の自動化ツール
監視・運用:
- Amazon CloudWatch: メトリクス監視とログ管理
- AWS X-Ray: 分散トレーシング
- Amazon OpenSearch: ログ分析とダッシュボード
セキュリティ:
- AWS IAM: アクセス制御の詳細設定
- AWS Secrets Manager: 機密情報の安全な管理
- AWS WAF: Webアプリケーションファイアウォール
データベース・ストレージ:
- Amazon DynamoDB: NoSQLデータベース
- Amazon S3: オブジェクトストレージ
- Amazon RDS: リレーショナルデータベース
これらの技術も同じ書籍で体系的に学べるため、効率的にAWSスキルを習得できます。
まとめ
今回は、AWS Lambdaを中心としたサーバーレス技術と、ECS・EKSのコンテナサービスについて解説しました。
重要なポイントをおさらいすると:
- Lambda: 短時間・イベント駆動の処理に最適
- ECS: AWS特化の簡単なコンテナ管理
- EKS: Kubernetes標準の高機能コンテナ管理
- 使い分け: 処理特性と要件に応じた適切な選択
- ハイブリッド: 複数技術の組み合わせで最適化
現代のアプリケーション開発では、これらの技術を適切に使い分けることが重要です。
まずは小さなプロジェクトから始めて、それぞれの特性を実際に体験してみてください。
そして、より深い理解のために書籍も活用して、実践的なスキルを身につけていきましょう!
サーバーレスとコンテナ、どちらも現代の開発には欠かせない技術です。継続的に学習して、効率的なシステム開発を目指していきましょう!
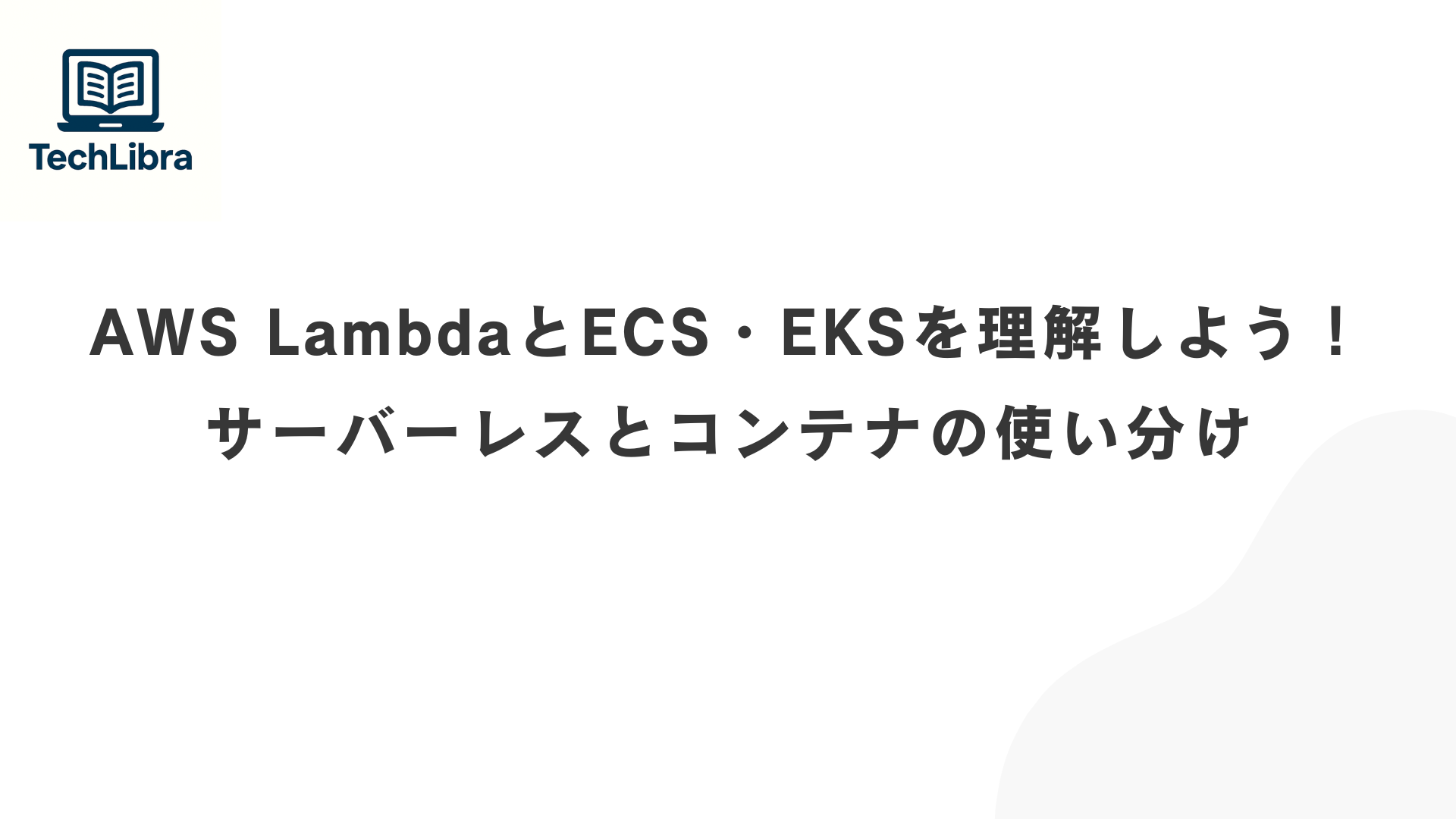

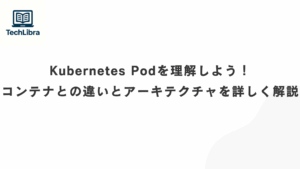

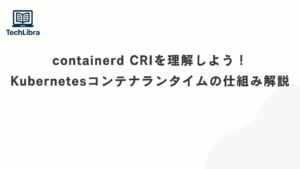
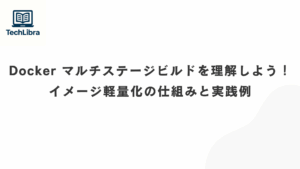
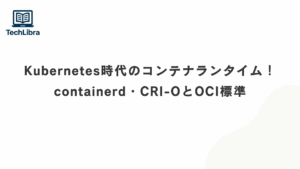
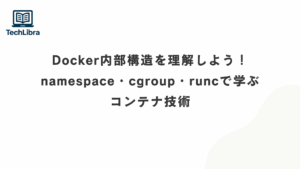
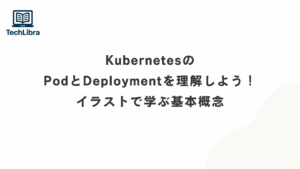
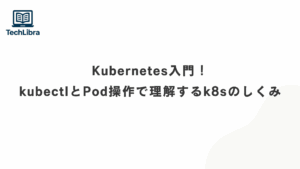
コメント