こんにちは!AWSを始めようと思って調べてみたら「EC2」「S3」という言葉がよく出てきませんか?
「なんだか難しそう…」「どこから手をつけていいか分からない」そんな風に感じているかもしれませんね。
私も最初は同じでした!「Elastic Compute Cloud?Simple Storage Service?」カタカナや英語ばかりで、何が何だか全然分からない状態でした。
でも大丈夫です!EC2とS3は一度理解してしまえば、AWSの他のサービスを学ぶ上でも重要な基盤になります。
今回は「図解即戦力 Amazon Web Servicesのしくみと技術が これ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]」を参考に、AWS EC2とS3の基本概念から実践的な使い方まで、初心者の方でも分かりやすく解説していきます!
AWSの基本!EC2とS3が重要な理由
クラウドコンピューティングの基本概念
まず、クラウドコンピューティングの基本的な考え方を理解しましょう。
従来のIT環境(オンプレミス):
- 物理的なサーバー機器の購入・設置
- データセンターの構築・管理
- ハードウェアの保守・運用
- 初期投資が大きく、拡張に時間がかかる
クラウド環境(AWS):
- 必要な時に必要な分だけ: リソースの動的な調達
- 従量課金: 使った分だけの支払い
- 即座の拡張: 数分でリソースを増減
- 保守不要: インフラ管理はAWSが担当
クラウドの3つの基本要素:
- コンピューティング: 計算処理を行うサーバー
- ストレージ: データを保存する領域
- ネットワーク: サービス間を接続する仕組み
この3要素の中で、コンピューティングを担うのがEC2、ストレージを担うのがS3です。
なぜEC2とS3から始めるべきなのか
EC2とS3は、AWSの中でも特に基本的で重要なサービスです。
EC2が重要な理由:
- AWSの中核: ほぼ全てのシステムでサーバーが必要
- 学習効果: サーバー管理の基本を学べる
- 応用性: 他のAWSサービスとの連携の基盤
- 実用性: Webサイト、アプリケーション、バッチ処理など幅広い用途
S3が重要な理由:
- データ保存の基盤: あらゆるデータの保存先
- 高可用性: 99.999999999%(イレブンナイン)の耐久性
- スケーラビリティ: 無制限の容量拡張
- コスト効率: 使った分だけの料金体系
学習の相乗効果:
- EC2とS3の組み合わせで実用的なシステムを構築可能
- 他のAWSサービスの多くがEC2・S3と連携
- 基本概念を理解することで他サービスの理解が容易に
実際の活用例:
- Webサイト: EC2でWebサーバー、S3で画像・CSS保存
- バックアップ: EC2のデータをS3に定期保存
- ログ分析: EC2で生成されたログをS3に蓄積・分析
この2つを理解することで、AWSの基本的なシステム構築ができるようになります。
Amazon EC2で仮想サーバーを理解しよう
EC2(Elastic Compute Cloud)とは
Amazon EC2は、クラウド上で仮想サーバー(インスタンス)を提供するサービスです。
EC2の基本概念:
- インスタンス: 仮想サーバーの実体
- 仮想化技術: 1台の物理サーバー上で複数の仮想サーバーを実行
- 弾力性(Elastic): 必要に応じてサーバー数やスペックを変更可能
- 従量課金: 使用時間に応じた料金
EC2の特徴:
- 即座の起動: 数分でサーバーが利用可能
- スケールアップ・ダウン: CPUやメモリの変更が容易
- 多様なOS: Linux、Windows、macOSなど
- グローバル展開: 世界各地のデータセンターで利用可能
従来のサーバーとの違い:
- 調達時間: 数週間 → 数分
- 初期費用: 数十万円 → 0円
- 保守: 自社対応 → AWS対応
- 拡張性: 物理制約あり → 制約なし
インスタンスタイプと選び方
EC2では、用途に応じて様々なインスタンスタイプが用意されています。
主要なインスタンスファミリー:
1. 汎用(General Purpose):
- t3, t4g: 基本的な用途、バースト性能
- m5, m6i: バランスの取れた性能
- 用途: Webサーバー、小規模データベース
2. コンピューティング最適化(Compute Optimized):
- c5, c6i: 高いCPU性能
- 用途: 科学計算、バッチ処理
3. メモリ最適化(Memory Optimized):
- r5, r6i: 大容量メモリ
- 用途: インメモリデータベース、リアルタイム分析
4. ストレージ最適化(Storage Optimized):
- i3, i4i: 高速なローカルストレージ
- 用途: 分散ファイルシステム、データウェアハウス
選び方のポイント:
- CPU重視: 計算処理が多い → c系
- メモリ重視: 大量データを扱う → r系
- バランス重視: 一般的な用途 → m系やt系
- コスト重視: 変動する負荷 → t系(バースト)
サイズの決め方:
- 小規模なら
nano、microから開始 - 本格運用なら
small、medium以上 - 負荷に応じて
large、xlargeなど
AMI(Amazon Machine Image)の活用
AMIは、インスタンスの「設計図」のような役割を果たします。
AMIとは:
- 定義: インスタンス起動に必要なテンプレート
- 内容: OS、アプリケーション、設定情報
- 利点: 同じ環境を素早く複製可能
AMIの種類:
1. AWS提供AMI:
- Amazon Linux: AWS最適化されたLinux
- Ubuntu: 人気のLinuxディストリビューション
- Windows Server: Microsoftの標準OS
- 特徴: セキュリティパッチ適用済み、AWS最適化
2. コミュニティAMI:
- 提供者: AWS利用者が作成・共有
- 内容: 特定用途向けの設定済み環境
- 注意: セキュリティ面での確認が必要
3. カスタムAMI:
- 作成者: 自分で作成
- 内容: 独自のアプリケーション、設定
- 利点: 完全にカスタマイズされた環境
AMI活用のメリット:
- 環境の統一: 開発・検証・本番で同じ環境
- 迅速なデプロイ: 設定済み環境の即座の複製
- 災害復旧: 障害時の迅速な復旧
- スケーリング: Auto Scalingでの自動増減
EC2インスタンスの作成と基本設定
インスタンス作成の流れ
実際にEC2インスタンスを作成する手順を見てみましょう。
基本的な作成手順:
1. AMIの選択:
- 用途に応じたOSの選択
- AWSが推奨するAMIを選択することを推奨
2. インスタンスタイプの選択:
- CPU、メモリ、ネットワーク性能の決定
- 最初は小さめから始めて後で変更可能
3. インスタンス詳細の設定:
- VPC: ネットワーク環境の選択
- サブネット: 配置場所の決定
- IAMロール: 権限の設定
4. ストレージの追加:
- ルートボリューム: OSがインストールされるディスク
- 追加ボリューム: 必要に応じてデータ用ディスク
5. タグの追加:
- 管理しやすくするためのラベル付け
- 例:Name=WebServer、Environment=Production
6. セキュリティグループの設定:
- ネットワークレベルのファイアウォール
- どのポートからのアクセスを許可するか
7. キーペアの設定:
- SSH接続のための認証キー
- 安全な場所への保存が重要
設定のポイント:
- 最初は最小限の設定から開始
- セキュリティ設定は慎重に
- タグ付けで管理を容易に
セキュリティグループとキーペア
EC2インスタンスのセキュリティを確保するための重要な仕組みです。
セキュリティグループ:
- 役割: インスタンスレベルのファイアウォール
- 制御: インバウンド(受信)・アウトバウンド(送信)トラフィック
- 設定単位: プロトコル、ポート番号、送信元IPアドレス
典型的な設定例:
Webサーバー用セキュリティグループ:
- HTTP (80): 0.0.0.0/0 (全世界からアクセス可)
- HTTPS (443): 0.0.0.0/0 (全世界からアクセス可)
- SSH (22): 自分のIPアドレスのみセキュリティグループのベストプラクティス:
- 最小権限の原則: 必要最小限のポートのみ開放
- 送信元の限定: 可能な限りIPアドレスを制限
- 命名規則: 用途が分かりやすい名前を付ける
- 定期的な見直し: 不要なルールの削除
キーペア:
- 用途: EC2インスタンスへのSSH接続認証
- 構成: 公開鍵(AWS保管)と秘密鍵(ユーザー保管)
- 形式: .pemファイル(Linuxの場合)
キーペアの管理:
- 安全な保存: 秘密鍵の厳重な管理
- バックアップ: 複数の安全な場所での保管
- 定期的な更新: セキュリティ向上のための鍵の更新
- アクセス制御: 必要な人のみがキーを持つ
Elastic IPとネットワーク設定
EC2インスタンスのネットワーク設定について理解しましょう。
IPアドレスの種類:
1. プライベートIPアドレス:
- 用途: VPC内での通信
- 特徴: インスタンス停止・開始でも変わらない
- 範囲: RFC 1918で定義されたプライベート範囲
2. パブリックIPアドレス:
- 用途: インターネットとの通信
- 特徴: インスタンス停止・開始で変わる
- 注意: 動的に割り当てられる
3. Elastic IPアドレス:
- 用途: 固定のパブリックIPアドレス
- 特徴: インスタンスに関連付けて使用
- 料金: 使用していない時は課金あり
Elastic IPが必要な場面:
- DNS設定: ドメイン名との紐付け
- 外部サービス連携: IPアドレス制限がある場合
- 高可用性: インスタンス切り替え時のIP維持
ネットワーク設定のベストプラクティス:
- VPC設計: 適切なサブネット分割
- パブリック/プライベート: 役割に応じた配置
- セキュリティ: 不要な外部アクセスは遮断
- Elastic IP: 本当に必要な場合のみ使用
配置パターンの例:
- Webサーバー: パブリックサブネット + Elastic IP
- データベース: プライベートサブネット + プライベートIPのみ
- バッチサーバー: プライベートサブネット + NAT Gateway経由でのインターネットアクセス
Amazon S3でオブジェクトストレージを活用
S3(Simple Storage Service)とは
Amazon S3は、インターネット対応のクラウドストレージサービスです。
S3の基本概念:
- オブジェクトストレージ: ファイル単位でのデータ管理
- REST API: HTTP/HTTPSでのアクセス
- 無制限容量: 理論上無制限のストレージ
- 高耐久性: 99.999999999%(イレブンナイン)の耐久性
従来のストレージとの違い:
ファイルシステム(従来):
- 階層的なフォルダ構造
- ブロック単位でのアクセス
- OSに依存した操作
オブジェクトストレージ(S3):
- フラットな名前空間
- オブジェクト単位でのアクセス
- Web API経由での操作
S3の特徴:
- スケーラビリティ: 自動的な容量拡張
- 可用性: 複数のデータセンターでの冗長化
- セキュリティ: 暗号化、アクセス制御
- 統合性: 他AWSサービスとのシームレス連携
主な用途:
- Webサイト: 静的コンテンツ(画像、CSS、JS)の配信
- バックアップ: データの長期保存
- データレイク: ビッグデータの蓄積・分析
- アーカイブ: 法令対応での長期保管
バケットとオブジェクトの概念
S3は「バケット」と「オブジェクト」という2つの基本要素で構成されます。
バケット:
- 定義: オブジェクトを格納するコンテナ
- 命名: グローバルに一意な名前が必要
- 作成場所: 特定のリージョンで作成
- 権限: バケットレベルでのアクセス制御
バケット命名のルール:
- 3~63文字の長さ
- 小文字、数字、ハイフンのみ使用可能
- IPアドレス形式は不可
- 例:
my-company-backup-2025
オブジェクト:
- 定義: バケット内に保存される個別のファイル
- サイズ: 0バイト~5TBまで
- キー: バケット内での一意な識別子
- メタデータ: オブジェクトに付随する情報
オブジェクトキーの例:
バケット名: my-website-assets
オブジェクトキー: images/logo.png
完全URL: https://my-website-assets.s3.amazonaws.com/images/logo.pngフォルダの概念:
- S3には実際のフォルダは存在しない
- オブジェクトキーの「/」で階層的な表示を実現
- 例:
documents/2025/report.pdf
管理のベストプラクティス:
- 命名規則: 一貫した命名パターン
- プレフィックス: 論理的なグループ分け
- バージョニング: 同名ファイルの履歴管理
- ライフサイクル: 古いファイルの自動削除・移動
ストレージクラスと料金最適化
S3では、用途に応じて複数のストレージクラスが用意されています。
主要なストレージクラス:
1. S3 Standard:
- 用途: 頻繁にアクセスするデータ
- 可用性: 99.99%
- 特徴: 高性能、低レイテンシ
- コスト: 最も高い
2. S3 Standard-IA(Infrequent Access):
- 用途: 月に1回程度のアクセス
- 可用性: 99.9%
- 特徴: 取得料金が発生
- コスト: Standardより安い
3. S3 Glacier:
- 用途: アーカイブ、長期保存
- 取得時間: 数分~数時間
- 特徴: 非常に低コスト
- 用途例: バックアップ、コンプライアンス
4. S3 Glacier Deep Archive:
- 用途: 年に1-2回のアクセス
- 取得時間: 12時間以内
- 特徴: 最も低コスト
- 用途例: 法令対応、長期アーカイブ
5. S3 Intelligent-Tiering:
- 用途: アクセスパターンが不明
- 特徴: 自動的にクラス変更
- コスト: 監視料金が追加
料金最適化の戦略:
- ライフサイクルポリシー: 時間経過による自動クラス変更
- アクセス分析: 実際の使用パターンの把握
- 削除ポリシー: 不要ファイルの自動削除
- マルチパートアップロード: 大きなファイルの効率的アップロード
ライフサイクルポリシー例:
- 30日後: Standard → Standard-IA
- 90日後: Standard-IA → Glacier
- 365日後: Glacier → Deep Archive
- 2555日後: 削除S3の実践的な使い方とセキュリティ
ファイルのアップロード・ダウンロード
S3へのファイル操作の基本的な方法を理解しましょう。
アクセス方法:
1. AWSマネジメントコンソール:
- 利点: GUIで直感的な操作
- 用途: 少数ファイルの手動操作
- 制限: 大量ファイルには不向き
2. AWS CLI:
- 利点: コマンドラインでの自動化
- 用途: バッチ処理、スクリプト
- 例:
aws s3 cp file.txt s3://my-bucket/
3. AWS SDK:
- 利点: プログラムからの操作
- 言語: Python、Java、Node.js、PHP等
- 用途: アプリケーションとの統合
4. サードパーティツール:
- 例: Cyberduck、WinSCP、s3cmd
- 利点: 使い慣れたインターフェース
アップロード時の考慮事項:
- ファイルサイズ: 5GB以上はマルチパートアップロード
- 暗号化: 転送時・保存時の暗号化設定
- メタデータ: Content-Type等の適切な設定
- 権限: アップロード後のアクセス権限
ダウンロード時の考慮事項:
- 帯域幅: 大容量ファイルの転送時間
- 権限: ダウンロード権限の確認
- 署名付きURL: 一時的なアクセス権の付与
- CloudFront: 高速配信のためのCDN活用
アクセス制御とバケットポリシー
S3のセキュリティは多層的なアクセス制御で実現されます。
アクセス制御の階層:
1. IAM(Identity and Access Management):
- 対象: AWSユーザー・ロール
- 粒度: サービス・リソースレベル
- 用途: AWS内のアクセス制御
2. バケットポリシー:
- 対象: バケット単位
- 形式: JSON形式のポリシー
- 用途: バケット全体のアクセス制御
3. オブジェクトACL:
- 対象: オブジェクト単位
- 粒度: 読み取り・書き込み権限
- 用途: 個別ファイルのアクセス制御
バケットポリシーの例:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-public-bucket/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:ExistingObjectTag/Environment": "public"
}
}
}
]
}セキュリティのベストプラクティス:
- 最小権限の原則: 必要最小限のアクセス権のみ付与
- パブリックアクセスの制限: 意図しない公開の防止
- MFA Delete: 重要ファイルの削除時にMFA要求
- ログ監視: CloudTrailでのアクセス履歴監視
静的Webサイトホスティング
S3の静的Webサイトホスティング機能を活用しましょう。
静的Webサイトホスティングとは:
- 機能: HTMLファイルをWebサイトとして公開
- 対象: HTML、CSS、JavaScript、画像ファイル
- 制限: サーバーサイド処理(PHP、Python等)は不可
- 利点: 低コスト、高可用性、高性能
設定手順:
- バケットの作成: Webサイト用バケット
- 静的ホスティング有効化: インデックス・エラードキュメントの指定
- ファイルのアップロード: HTML、CSS、画像等
- パブリックアクセス許可: 全世界からの読み取り権限付与
- カスタムドメイン: Route 53での独自ドメイン設定
フォルダ構造の例:
my-website-bucket/
├── index.html
├── error.html
├── css/
│ └── style.css
├── js/
│ └── script.js
└── images/
└── logo.png活用例:
- 企業サイト: コーポレートサイト、ランディングページ
- ポートフォリオ: 個人作品集、履歴書サイト
- ドキュメント: API仕様書、マニュアル
- SPA: Single Page Application(React、Vue.js等)
CloudFrontとの組み合わせ:
- CDN: 世界中での高速配信
- HTTPS: SSL/TLS証明書の自動適用
- カスタムドメイン: 独自ドメインでのアクセス
- キャッシュ: 静的ファイルの効率的配信
料金メリット:
- サーバー管理コスト不要
- 従量課金(リクエスト数・転送量)
- Auto Scalingによる高トラフィック対応
- 99.999999999%の高耐久性
EC2とS3の連携パターン
EC2からS3へのデータ保存
EC2とS3を連携させることで、効率的なデータ管理が可能になります。
連携の基本パターン:
1. アプリケーションデータの保存:
- ユーザーアップロードファイル
- 生成されたレポート・画像
- ログファイルの長期保存
2. バックアップ・アーカイブ:
- データベースのバックアップ
- 設定ファイルの保存
- システムスナップショット
3. 静的コンテンツの配信:
- Webサイトの画像・CSS・JavaScript
- ダウンロード用ファイル
- メディアコンテンツ
実装方法:
AWS CLI使用:
# ファイルのアップロード
aws s3 cp /var/log/application.log s3://my-backup-bucket/logs/
# フォルダの同期
aws s3 sync /var/www/html/images s3://my-website-bucket/images/
# バックアップスクリプト
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y%m%d)
mysqldump -u user -p database > backup-$DATE.sql
aws s3 cp backup-$DATE.sql s3://my-backup-bucket/db-backups/プログラムでの実装(Python例):
import boto3
from datetime import datetime
s3 = boto3.client('s3')
# ファイルアップロード
def upload_file(local_file, bucket, s3_key):
try:
s3.upload_file(local_file, bucket, s3_key)
print(f"Upload successful: {s3_key}")
except Exception as e:
print(f"Upload failed: {e}")
# 使用例
upload_file(
'/var/log/app.log',
'my-backup-bucket',
f'logs/app-{datetime.now().strftime("%Y%m%d")}.log'
)IAMロールの設定:
- EC2インスタンスにS3アクセス用のIAMロールを付与
- 最小権限の原則に基づく権限設定
- アクセスキーの埋め込みを避ける
バックアップとスナップショット
システムの可用性を高めるためのバックアップ戦略を考えてみましょう。
バックアップの種類:
1. EBSスナップショット:
- 対象: EC2のルートボリューム、データボリューム
- 特徴: ブロックレベルの増分バックアップ
- 利点: 迅速な復旧、ポイントインタイム復元
2. S3バックアップ:
- 対象: アプリケーションデータ、ログファイル
- 特徴: オブジェクトレベルのバックアップ
- 利点: 長期保存、低コスト
3. AMIバックアップ:
- 対象: システム全体の設定
- 特徴: 完全なシステムイメージ
- 利点: 迅速な環境復旧
自動バックアップの実装:
Lambda + EventBridge:
import boto3
from datetime import datetime, timedelta
def lambda_handler(event, context):
ec2 = boto3.client('ec2')
# 7日より古いスナップショットを削除
snapshots = ec2.describe_snapshots(OwnerIds=['self'])
for snapshot in snapshots['Snapshots']:
start_time = snapshot['StartTime'].replace(tzinfo=None)
if datetime.now() - start_time > timedelta(days=7):
ec2.delete_snapshot(SnapshotId=snapshot['SnapshotId'])バックアップのベストプラクティス:
- 3-2-1ルール: 3つのコピー、2つの異なるメディア、1つはオフサイト
- 定期実行: 自動化による確実なバックアップ
- 復旧テスト: 定期的な復旧手順の確認
- 世代管理: 適切な保存期間の設定
ログファイルの保存と分析
システムログの効率的な管理と分析について見てみましょう。
ログ管理の課題:
- ローカルディスクの容量制限
- ログファイルの散在
- 検索・分析の困難さ
- 長期保存のコスト
S3を活用したログ管理:
1. ログ収集:
- CloudWatch Agentでの自動転送
- 定期的なS3へのアップロード
- リアルタイムストリーミング(Kinesis)
2. ログ構造化:
s3://my-log-bucket/
├── application-logs/
│ ├── year=2025/month=01/day=15/hour=10/
│ └── year=2025/month=01/day=15/hour=11/
├── access-logs/
│ ├── year=2025/month=01/day=15/
└── error-logs/
├── year=2025/month=01/day=15/3. ログ分析:
- Athena: SQLでのログ分析
- OpenSearch: 全文検索・可視化
- QuickSight: ダッシュボード作成
- Glue: ETL処理でのデータ変換
コスト最適化:
- ライフサイクルポリシー: 古いログの自動アーカイブ
- 圧縮: gzip等での容量削減
- パーティション: 効率的なクエリのための構造化
- Intelligent Tiering: アクセスパターンに基づく自動最適化
EC2・S3をさらに深く学ぶために
書籍で学べる実践的な運用技術
今回の記事では、EC2とS3の基本概念から実践的な活用法まで解説しました。
「図解即戦力 Amazon Web Servicesのしくみと技術が これ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]」では、さらに詳細な運用技術について学ぶことができます。
書籍で学べる詳細内容:
- 高度なEC2運用: Auto Scaling、Load Balancer、Spot Instance
- S3の詳細機能: Cross-Region Replication、Event Notification
- セキュリティ強化: 暗号化、VPC Endpoint、PrivateLink
- パフォーマンス最適化: インスタンスストア、EBS最適化
- 料金最適化: Reserved Instance、Savings Plans
特に図解による説明が豊富で、複雑なアーキテクチャも視覚的に理解できます。
実務で重要な高度なトピック:
- 災害復旧設計: マルチAZ、クロスリージョン構成
- 監視・運用: CloudWatch、Systems Manager
- 自動化: CloudFormation、Terraform
- コンプライアンス: 法令対応、セキュリティ基準
- 移行戦略: オンプレミスからの段階的移行
次に学ぶべき関連サービス
EC2とS3を理解したら、次はこれらのサービスも学習することをおすすめします:
コンピューティング関連:
- Auto Scaling: 自動的なサーバー増減
- Elastic Load Balancing: 負荷分散
- Lambda: サーバーレスコンピューティング
- ECS/EKS: コンテナオーケストレーション
ストレージ関連:
- EBS: ブロックストレージ
- EFS: ファイルシステム
- FSx: フルマネージドファイルシステム
- Storage Gateway: ハイブリッドストレージ
ネットワーク関連:
- VPC: 仮想プライベートクラウド
- CloudFront: CDN(コンテンツ配信ネットワーク)
- Route 53: DNSサービス
- Direct Connect: 専用線接続
データベース関連:
- RDS: リレーショナルデータベース
- DynamoDB: NoSQLデータベース
- ElastiCache: インメモリキャッシュ
- Aurora: 高性能マネージドデータベース
運用・監視関連:
- CloudWatch: 監視サービス
- CloudTrail: API監査ログ
- Systems Manager: システム管理
- Config: リソース設定追跡
これらのサービスも同じ書籍で体系的に学べるため、効率的にAWSスキルを向上させることができます。
まとめ
今回は、AWS EC2とS3について、基本概念から実践的な活用法まで詳しく解説しました。
重要なポイントをおさらいすると:
- EC2: クラウド上の仮想サーバー、柔軟なスケーリングが可能
- S3: 高耐久性のオブジェクトストレージ、無制限容量
- 連携: EC2とS3を組み合わせた効率的なシステム構築
- セキュリティ: IAM、セキュリティグループ、バケットポリシーでの多層防御
- コスト最適化: ストレージクラス、ライフサイクルポリシーの活用
EC2とS3は、AWSの基盤となる重要なサービスです。この2つを理解することで、他のAWSサービスも理解しやすくなります!
まずは小さなプロジェクトから始めて、実際にインスタンスを作成したり、ファイルをS3にアップロードしたりして、体験してみてください。
そして、より高度な機能や他のサービスとの連携も学んで、本格的なクラウドシステムを構築できるようになりましょう!
AWSの世界は広大ですが、一歩ずつ着実に学習していけば、必ずスキルアップできます。継続的な学習で、クラウドエンジニアとしての力を身につけていきましょう!
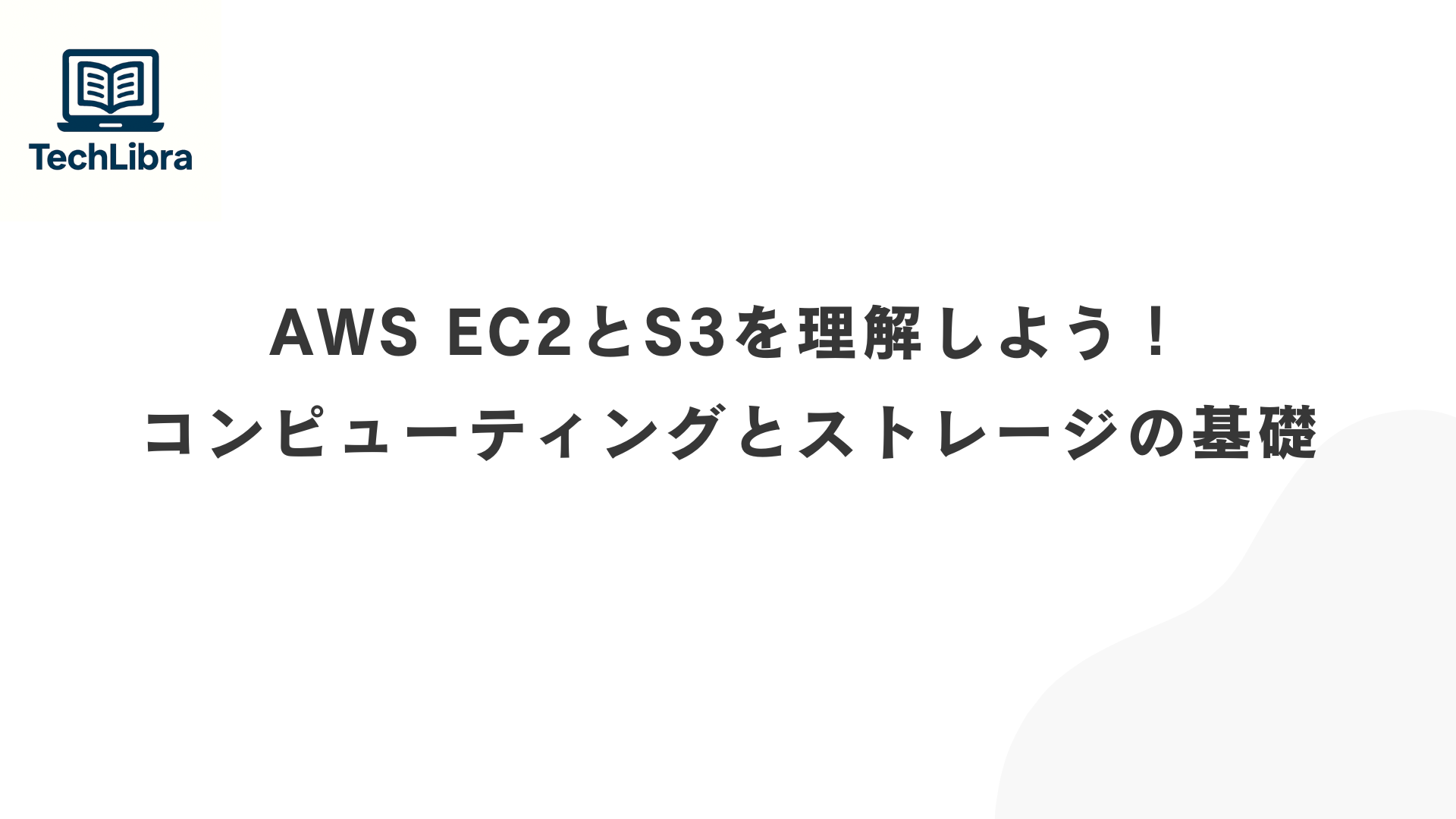

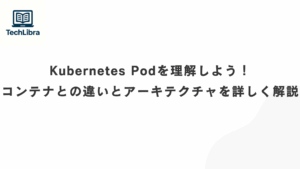

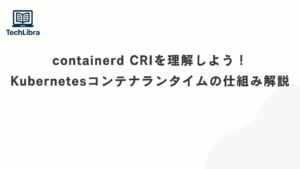
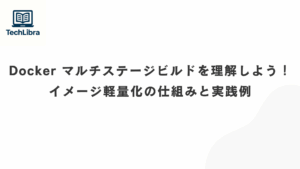
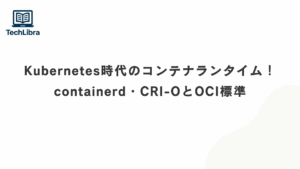
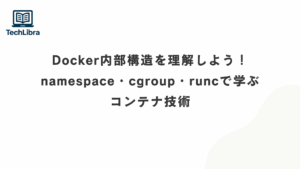
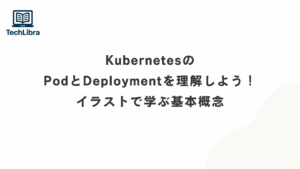
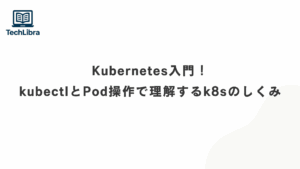
コメント